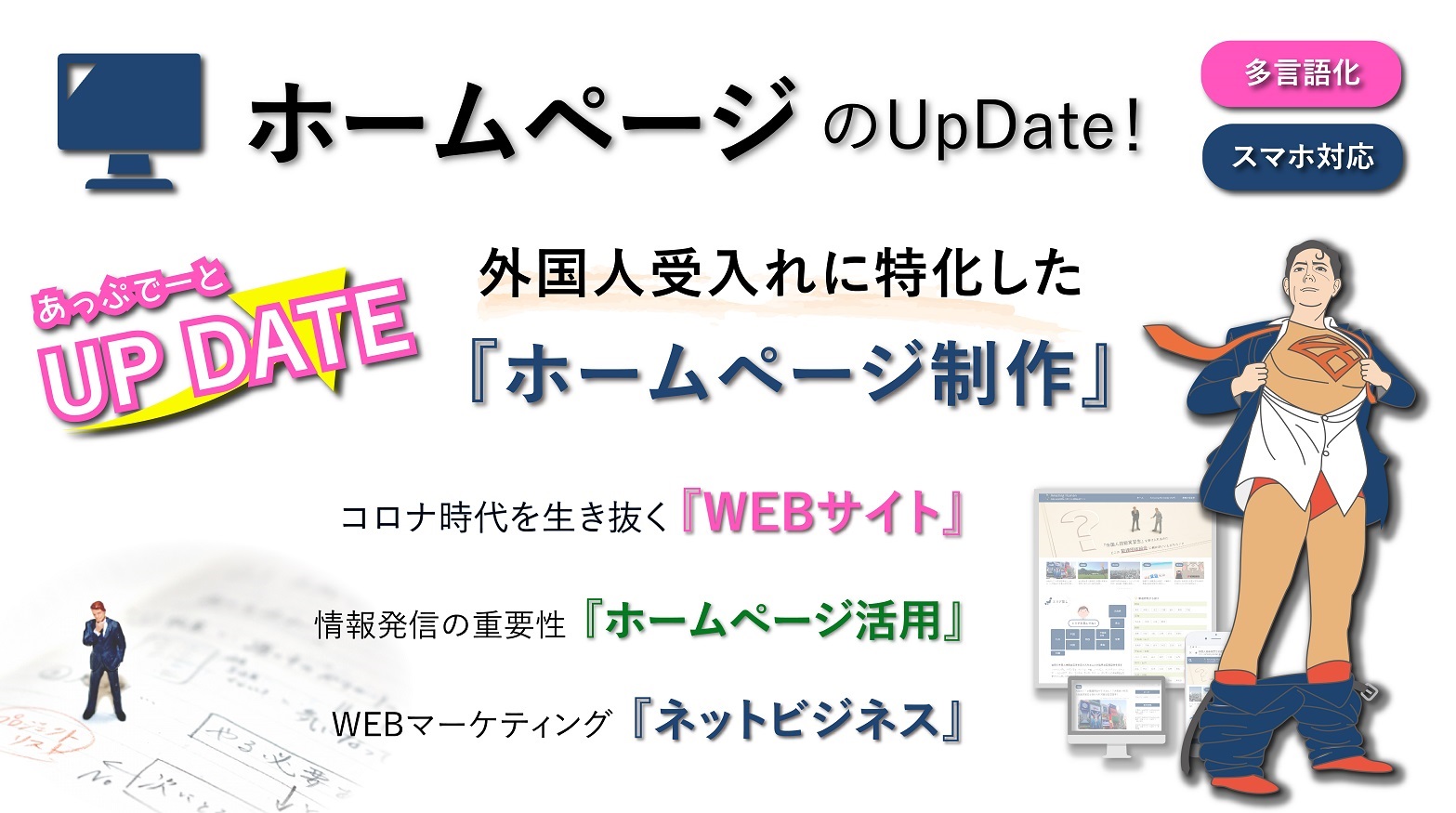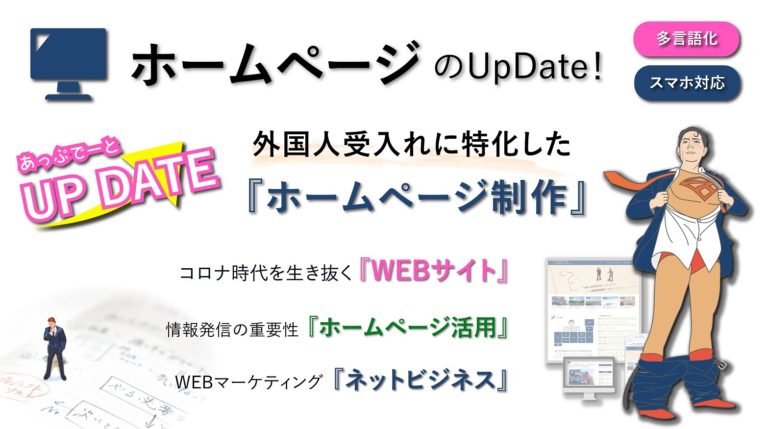育成就労制度と特定技能改正の最新動向:監理支援機関・登録支援機関の上限制と実務への影響
2025年4月28日、育成就労および特定技能に関する改正法に基づく意見募集(パブリックコメント)が正式に開始されました。
今回は、その中でも注目される「監理支援機関・登録支援機関の体制要件(上限ルール)」について、わかりやすく整理・解説します。
監理支援機関とは、現在の「監理団体」と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)への監理・指導、そして育成就労外国人の支援・保護などを行う機関です。
新制度「育成就労」では、この監理・支援・保護の機能をより適切に果たせるよう、許可要件の見直しと機能強化が進められる方向となっています。
覚えておくべき2つの上限基準
- 育成就労:職員1人あたり 8社未満・40名未満
- 特定技能:職員1人あたり 10社未満・50名未満
この上限制は、あくまで「最低限ここまでは絞ってほしい」という足切りラインであり、上限=適正規模ではない点に注意が必要です。
なぜ上限が設定されたのか?背景と目的
育成就労制度は、現行の技能実習・特定技能制度で浮き彫りになった「支援・監理の不十分さ」を是正するために導入されます。
行政機関は、支援スタッフ1人あたりの対応範囲が広すぎると、十分なフォローができない点を問題視しており、適正規模での支援体制を求める方向性が明確になりました。
この上限制は、「監理の質」「支援の深さ」を確保するための制度的ブレーキとして位置づけられています。
よくある質問(Q&A)
Q:育成就労8社40名+特定技能10社50名=合算して18社90名までOK?
A:監督官庁が異なるため、理論上は合算容認の案もありますが、現時点では確定していません。育成就労制度の厳格化の流れから見ると、実際には「品質担保の現場体制」が整っていない場合、行政指導の対象となる可能性があります。
上限確定後に起こる「3つの実務インパクト」
1. 人件費が大幅増加
上限を守るには、企業数を減らすか、職員を増やすかの選択が迫られます。
スタッフを増やせば、給与・社会保険・夜間対応手当などの固定費が一気に膨らみます。
2. 支援費の改定の可能性
支援費は「人数 × 単価」で構成されるため、上限が固定されれば粗利も一定化。
スタッフ増によるコスト増を吸収するため、支援費単価の見直しが業界全体で必要になると見られます。
3. 監査・顧問契約費の上昇
チェック項目が増え、監査回数が増えることで、社労士・弁護士などの外部契約コストも上昇傾向に。
制度の厳格化に伴い、監理・支援事業全体の運営コストは今後さらに増加する見通しです。
今後の実務対応:体制づくりの第一歩は「送り出し機関の見直し」
育成就労制度では、入国前に外国人が一定の日本語力を有していることが求められます。
これにより、送り出し機関の教育・選抜体制の重要性がさらに高まります。
- N5レベル=育成就労の入国要件
- N4レベル=特定技能への移行要件
基準を満たさない場合は、入国後に「認定日本語教育機関」で講習を受ける必要があり、企業側の負担が増大します。
まとめ:今後の方向性と業界へのメッセージ
育成就労・特定技能の制度改正は、単なる名称変更ではなく、「支援・監理の品質向上」を狙った構造的改革です。
- 職員あたりの担当数に上限が設定され、支援の質が重視される
- 人的リソース・コストの見直しが急務となる
- 送り出し教育の再構築が必要不可欠
今後も当サイトでは、最新の法令情報や体制整備のポイントを継続的に発信してまいります。
👉 最新情報・資料ダウンロードはこちら:
育成就労・特定技能 改正法ガイドページ